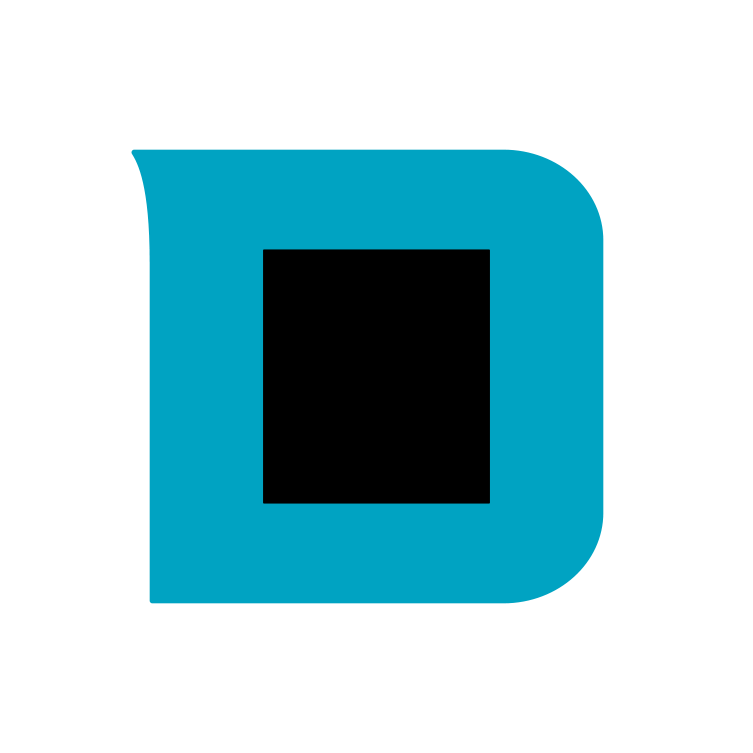「気持センシングラボ」対談 第2回
技術と解釈の組み合わせで新しいリサーチ手法を生む
大広ほか計4社のコラボレーションによってスタートした「気持センシングラボ」(ご参考:プレスリリース)。生体反応をセンシングして生活者の本心に迫ることを目指すこのプロジェクトの技術面をリードしているのが、ニューロマーケティングに取り組むSOOTHです。同社の取締役:CDOの𠮷澤貴幸と大広の山口大道が、気持センシングラボの可能性やビジョンについて語り合いました。
本記事は、博報堂DYグループ“生活者データ・ドリブン”マーケティング通信に掲載されたものを転用しています。

右:株式会社大広 東京アクティベーションデザインビジネスユニット カスタマープロモーション局デジタルプロモーショングループ プロデューサー 山口大道
どうすれば生活者の「本心」をつかむことができるのか
山口:𠮷澤さんは、広告会社のクリエイティブディレクターなどを経て、広告映像制作会社のAOI Pro.に入社されたのですよね。広告会社から制作会社というキャリアはかなりユニークだと思います。
𠮷澤:あまりないケースですが、デザイナーやフロントエンドエンジニアなどでチームを作れる環境はとても意義があります。僕はもともと日本の広告会社と外資系広告会社でほぼ10年ずつ働いたのですが、その両方を経験した人も多くはないと思います。
山口:SOOTHはAOI Pro.からスピンオフしてできたわけですが、何を目指して設立した会社なのか、改めて説明していただけますか。
𠮷澤:外資系広告会社はリサーチを非常に重視しており、クリエイティブディレクターが商品のリサーチ段階から関わるのは当たり前で、僕も何度もリサーチの現場に立ち会ってきました。そこでいつも感じていたのは、こういうことでした。
例えばフォーカスグループインタビューの場合、声の大きい人の意見をみんなが聞いてしまい、別の意見がなかなか言えない。設問数の多いアンケートでは、最後の方はどうしても流し気味に答えてしまう人が多い。つまり、従来のリサーチ手法では、生活者の「本心」がなかなかわからないということです。どうすれば本心をつかめるか──。それが以前からの僕の問題意識でした。
山口:今までのリサーチ技術は、仮説をつくるのには有効でも、現代の生活者の本音に迫ることはなかなかできない。そういうことですよね。僕もまったく同じ問題意識をもっていました。
𠮷澤:ええ。そこで、脳波や視線を測定して生活者の本心に迫るリサーチ手法に取り組もうと考えて立ち上げたのがSOOTHです。SOOTHのメンバーのほとんどは、AOI Pro.の旧「体験設計部」からの出向です。「体験設計」とは、アプリケーション、映像、ネット配信の技術などを組み合わせてソリューションをつくり、それによって生活者の新しい体験や価値を創出することを意味しています。したがってソリューションはいろいろなものの相互作用で成立する一種のエコシステムでなければならないのですが、そのすべての要素を僕たちがもっているわけではありません。エコシステムをつくり、それを拡張していくには、社外の専門家の皆さんとのコラボレーションが必須です。

山口:それが気持センシングラボに参画した理由ということですね。
𠮷澤:そういうことです。もっとも、実はコラボのオファーはいろいろなところからいただいていたんです。その中で山口さんのオファーが一番熱かった。それが決め手でしたね(笑)。
山口:ありがとうございます(笑)。僕は、アドテック東京に出展されていた御社のVRの技術を見て、「すごく先進的なことをやっている!」と思ってオファーさせていただいたんです。𠮷澤さんが気持センシングラボに求めたのは、具体的にどういうものだったのでしょうか。
𠮷澤:何より魅力的だったのは、大広を含む博報堂DYグループがもつ、クライアントとのタッチポイントの豊富さです。そのタッチポイントから吸い上げられるクライアントのニーズを知りたいと思いました。ソリューションのエンジンに磨きをかけようとしても、リアルなニーズがわからなければ、結局独りよがりのものをつくってしまうことになります。しかし、僕たちにはニーズを汲み取ることができる独自のタッチポイントがあまりありません。もし山口さんたちとご一緒できれば、クライアント目線、ユーザー目線でのソリューション開発ができるに違いない。そう考えたわけです。
発展のチャンスを迎えたニューロマーケティング
山口:SOOTHという社名。これもとてもユニークですが、どんな意味があるのですか。
𠮷澤:会社を立ち上げるときに考えたのは、覚えられやすく、かつ理屈が通っている社名にしたいということでした。でもそういうネーミングって、すでに使われていることが多いんですよ。僕たちがこの会社で目指したのは、生活者の本心、つまり「真実」をつかむことです。真実は英語では「Truth」ですが、ストレート過ぎるかなと。そこでいろいろ調べたところ、真実を意味する古語に「Sooth」という言葉があることがわかりました。さらに、これに「Sayer」をつけて「Soothsayer」とすると「預言者」という意味になるらしい。つまり、表面から見てもわからない深層を洞察して、真実を言い当てる人、ということです。
山口:𠮷澤さんが目指すものにぴったりのネーミングだったわけですね。これまでの実績についてもお聞かせいただけますか。
𠮷澤:いろいろやっていますが、例えば、パチンコの新しい台を発表するプロモーションの一環で、パチンコユーザーに脳波計をつけてもらい、プレイ中に感じたことを「脳内モニター」というアプリで可視化するということをやりました。考えていること、感じていることがすべてリアルタイムで文字になる仕組みで、これによって、アンケートやインタビューからは見えてこない本当の反応を把握することが可能になります。それから、アスリートやアーティストがよく言う「ゾーンに入る」という状態を、脳波計を使って捉える実験もやっています。

山口:集中力がぎりぎりまで高まって、パフォーマンス力が最大になる状態のことですよね。
𠮷澤:ざっくりいうと、α波とβ波が同時に強く計測される状態のことなのですが、これを、曲を演奏している3人の演奏家や、演奏家と聴衆の両方に脳波計をつけてもらって視覚化しました。
山口:実際のところ、ニューロマーケティングでできることって、どのくらいあるのでしょうか。正直、倫理的な問題が指摘されることもありますし、期待値が先走りしているという印象もあります。
𠮷澤:脳波の中にもわかりやすいものとそうではないものがありますから、「脳波を測定すればあらゆることがわかる」とは言えませんよね。しかし、ニューロマーケティングが大きく発展するチャンスがあるとすれば、それはまさに今であると僕は考えています。その大きな理由は、デバイスのコストにあります。2016年は「VR元年」と呼ばれていましたが、それはデバイスの価格が下がったことで一気に普及のフェーズに入ったからです。現在、脳波計デバイスがまさにそのフェーズにあります。大学で使う脳波計は依然200万円から300万円ほどしますが、この一年ほどの間に1万円程度で買える脳波計もどんどん発売されています。性能が高いものも少なくありません。

さらに脳波計の装着方法も変わってきています。以前は、ウエット式といって、頭にゼリーを塗って、針のついたセンサーを32カ所につけて装着するような機器が一般的でした。これではマーケティングリサーチに気軽に使うというわけにはいきません。それが最近ではゼリーなどを使わないドライ式になり、センサーは4つ、メーカーによっては1つだけのものも登場しました。ようやく「簡単に使えるデバイス」になったわけです。
「解釈」や「意味づけ」がなければマーケティング手法にはならない
山口:これでニューロマーケティングは一気に花開くと。
𠮷澤:しかし、問題はもう一つあります。技術が進歩して、デバイスのコストが下がっても、測定によって得られたデータを「解釈」する方法がなければ、マーケティングには使えません。
山口:ビッグデータがどれだけあっても、生活者の行動の「意味づけ」ができなければデータはただのデータに過ぎない。それと同じですね。
𠮷澤:そのとおりです。測定データに対する「解釈」「意味づけ」がミッシングピースになっていたために、ニューロマーケティングはこれまで普及してこなかったわけです。僕が気持センシングラボに非常に大きな期待を寄せているのは、僕たちが開発したソリューションによって得られたデータを、マーケティングのプロがしっかりと「解釈」してくれるという座組が成立すると思うからです。

山口:クライアントとの接点からニーズや課題を汲み上げて、それを解決できる技術を提示し、そこから得られたものを解釈して、マーケティングの戦略にまでつなげていく。そこまでをワンストップできるのが理想ですよね。
𠮷澤:それはすなわち「体験設計のフレーム」をつくることだと僕は思っています。例えば、CMには成功例とそうではない例がありますよね。その両方のCMを見た生活者の生体反応を蓄積することで「教師データ」をつくることができます。それが十分な量集まれば、CMの内容と生活者の反応、その成果の対応関係の「パターン」が見えてきます。それが体験設計のフレームになるわけです。
山口:こういう生体反応が出れば、こういう結果になる可能性が高い──。そんなエビデンスをつくるフレームということですね。
𠮷澤:そういうことです。生体反応には、脳波だけではなく、視線の動きなども含まれます。VRのデバイスを使うと、比較的簡単に視線の動きを把握することができます。見ている映像のどの部分に視線が動くかがわかるので、最も見られるところに最も見せたい商品を置くことが可能になります。いわば、センシングとクリエイティブの組み合わせが実現するということです。
山口:それは非常に重要な観点だと思います。データがクリエイティブに新しい気づきを与えるということですから。ものをつくるには経験や勘がもちろん重要です。でもそれだけでは見えないこともある。それをデータが手助けするということですよね。
𠮷澤:オンライン広告では、コミュニケーションの成果をはっきり出すことが求められます。今後は、マス広告を含めたあらゆるマーケティングコミュニケーションにエビデンスが求められるようになるでしょう。なぜなら、決裁者がそれを必要とするようになるからです。今後はおそらく、「結果はわからないけれど、面白いからやってみよう」という判断は少なくなっていくはずです。
そうなると、クリエイティブにもデータを生かして結果に確実につなげていくスキルが必要になります。いわばデータクリエイティブ、あるいはサイエンスクリエイティブ。そういう新しい方法を気持センシングラボから生み出していければいいですよね。
これまでになかったビジョンを多くの人に見せていきたい
山口:気持センシングラボから生まれるアウトプットには、制限がないと僕は思っています。もちろんマネタイズは重要ですが、それだけでなく、新しい発想法やそれを生み出すノウハウを獲得して、これまでになかったビジョンを多くの人に見せていくこと。それがこの取り組みの本質なんじゃないかと。

𠮷澤:気持センシングラボについてニューヨークで映画を撮っている先輩に話したところ、「ぜひやってほしいことがある」と言われました。それは、発達障がいや言語障がいがある人が考えていること、感じていることを可視化することです。現在の教育は健常者向けのものが多く、そういった人たちの才能を伸ばす方法がわからない。もし、その人たちの「真実」がわかれば、それにフィットした教育方法を編み出すことができる。そんなことをアメリカでいろんな人に会って感じたそうです。
この発想は、例えば子どもを対象にしたリサーチにも当てはまると思います。絵本を読んでいるときや飲み物を飲んでいるときの子どもの本心を知ることができれば、それを新しいマーケティングの手法としていくことができます。従来のアンケートには、きちんと答えられない子どももいますからね。
山口:これまでになかった新しい物差しを提示することができるわけですよね。そのためにも、僕はSOOTHに気持センシングラボの「心臓」になっていただきたいと考えています。
𠮷澤:このラボに加わったことで、真実を求める旅の大きなステップを踏み出すことができたと僕は感じています。今後、「心臓」からどう血をめぐらせていくか、一緒に考えていきましょう。
“生活者データ・ドリブン” マーケティング通信
http://seikatsusha-ddm.com/
『博報堂DYグループ “生活者データ・ドリブン” マーケティング通信』は、グループ横断の“生活者データ・ドリブン”マーケティング領域における情報発信サイト。
博報堂DYグループの各事業会社が連携し、“生活者データ・ドリブン”マーケティングに関するソリューションの情報や、生活者データの活用実績のある現場社員の知見やノウハウ、当該領域の最新ニュース等を発信。